広告

「イーサリアムにはなぜ発行上限がないのか?」と疑問に思ったことはありませんか?ビットコインは2,100万枚の発行上限があるのに対し、イーサリアムには明確な上限が設定されていません。しかし、EIP-1559やPoSへの移行によって、イーサリアムは発行量を抑える仕組みを取り入れ、デフレ資産に近づきつつあります。
本記事では、イーサリアムの発行上限がない理由、供給モデルの仕組み、EIP-1559による影響、ビットコインとの違い、そして今後の展望について詳しく解説します。イーサリアムの未来を理解し、投資の参考にしてみてください!
イーサリアムを買うなら「コインチェック」がおすすめ!
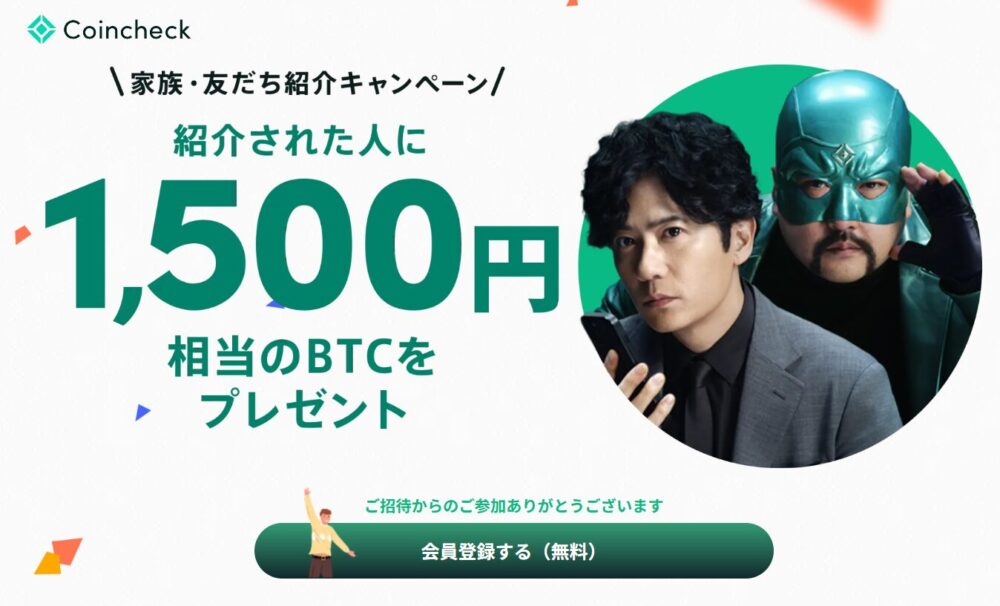
→当サイト限定!初めての「コインチェック」ご利用で1500円相当のビットコインがもらえる!
イーサリアムとは?基本をおさらい

ポイント
・イーサリアムの概要と特徴
・ビットコインとの違い
・イーサリアムの発行と供給モデル
・スマートコントラクトとは?
・イーサリアムのアップデートと進化
イーサリアムの概要と特徴
イーサリアム(Ethereum)は、分散型アプリケーション(DApps)を開発できるブロックチェーンプラットフォームです。2015年にヴィタリック・ブテリン氏らによって開発され、スマートコントラクトを実行できる点が特徴です。これにより、中央管理者なしで自動的に契約を実行できる仕組みが可能となりました。
ビットコインが「価値の保存」に特化しているのに対し、イーサリアムは「プログラム可能なブロックチェーン」としてさまざまな用途に利用されます。DeFi(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)、DAO(分散型自律組織)など、多くの分野で活用されています。
ビットコインとの違い
イーサリアムとビットコインにはいくつかの大きな違いがあります。
| 項目 | イーサリアム | ビットコイン |
|---|---|---|
| 主な目的 | スマートコントラクトとDAppsの実行 | 価値の保存・決済手段 |
| 発行上限 | なし | 2,100万枚 |
| コンセンサス機構 | PoS(プルーフ・オブ・ステーク) | PoW(プルーフ・オブ・ワーク) |
| トランザクション速度 | 約15秒 | 約10分 |
| スマートコントラクト | 可能 | 不可 |
このように、ビットコインは「デジタルゴールド」としての役割を持つのに対し、イーサリアムは「分散型アプリの基盤」としての機能を持っています。
イーサリアムの発行と供給モデル
イーサリアムは、もともとPoW(プルーフ・オブ・ワーク)を採用していましたが、2022年の「The Merge(マージ)」によりPoS(プルーフ・オブ・ステーク)へ移行しました。PoSでは、イーサリアムをステーク(預け入れ)することでネットワークの運用に参加し、新たなETH(イーサリアムの通貨単位)を獲得できます。
また、イーサリアムの供給量は一定ではなく、毎年新たにETHが発行される一方で、一部のETHがバーン(焼却)される仕組みが導入されています。
スマートコントラクトとは?
スマートコントラクトは、ブロックチェーン上で契約を自動実行できるプログラムです。例えば、「ある条件を満たしたら自動的に支払いを行う」といった処理を、仲介者なしで実行できます。これにより、金融取引やNFTの売買、サプライチェーン管理など、さまざまな分野での活用が広がっています。
イーサリアムのアップデートと進化
イーサリアムは継続的にアップデートが行われています。代表的なものに以下のようなものがあります。
- EIP-1559(2021年):取引手数料の改善とETHのバーン導入
- The Merge(2022年):PoWからPoSへの移行
- シャーディング(今後予定):ネットワークのスケーラビリティ向上
これらのアップデートにより、イーサリアムはより効率的で持続可能なネットワークへと進化を続けています。
イーサリアムに発行上限がない理由

ポイント
・発行上限がない設計思想
・インフレとネットワークの持続性
・セキュリティとマイナー(バリデーター)への報酬
・長期的な供給管理の仕組み
・ビットコインと異なる経済モデル
発行上限がない設計思想
ビットコインは「デジタルゴールド」として設計され、発行上限が2,100万枚に固定されています。しかし、イーサリアムは「世界の分散型コンピュータ」として設計されており、発行上限を設けることは最初から想定されていませんでした。
イーサリアムの開発者たちは、ネットワークの安全性と持続可能性を優先し、必要に応じて供給量を調整するモデルを採用しています。
インフレとネットワークの持続性
イーサリアムが継続的に新しいETHを発行する理由のひとつは、ネットワークの維持と安全性のためです。
もし発行上限があると、報酬が減ることでバリデーター(PoSの場合)やマイナー(PoWの場合)の参加意欲が低下し、ネットワークの安全性が損なわれる可能性があります。イーサリアムは適度なインフレを維持することで、ネットワークの維持を安定させています。
セキュリティとマイナー(バリデーター)への報酬
イーサリアムのバリデーター(PoS)には、新たに発行されたETHが報酬として支払われます。発行量を抑えすぎると、報酬が減少し、ネットワークの分散性や安全性が低下する恐れがあります。
また、EIP-1559の導入により、取引手数料の一部がバーンされるため、発行されるETHが必ずしも増え続けるわけではありません。
長期的な供給管理の仕組み
イーサリアムは「適切な供給量を維持する」という設計思想に基づいています。EIP-1559の導入により、ETHの供給量は需要と供給のバランスによって調整される仕組みになりました。
これにより、発行上限はないものの、無制限に増え続けることはなく、需給バランスによって「適度な供給量」が維持されるようになっています。
ビットコインと異なる経済モデル
ビットコインは発行上限があるため、供給が限られ、希少性が価値を生み出す仕組みです。一方、イーサリアムは適度なインフレを維持しながら、ネットワークの発展と安全性を確保する設計になっています。
この違いにより、ビットコインは「貯蔵価値」としての役割が強く、イーサリアムは「ユーティリティ(活用性)」を重視した経済モデルとなっています。
イーサリアムを買うなら「コインチェック」がおすすめ!
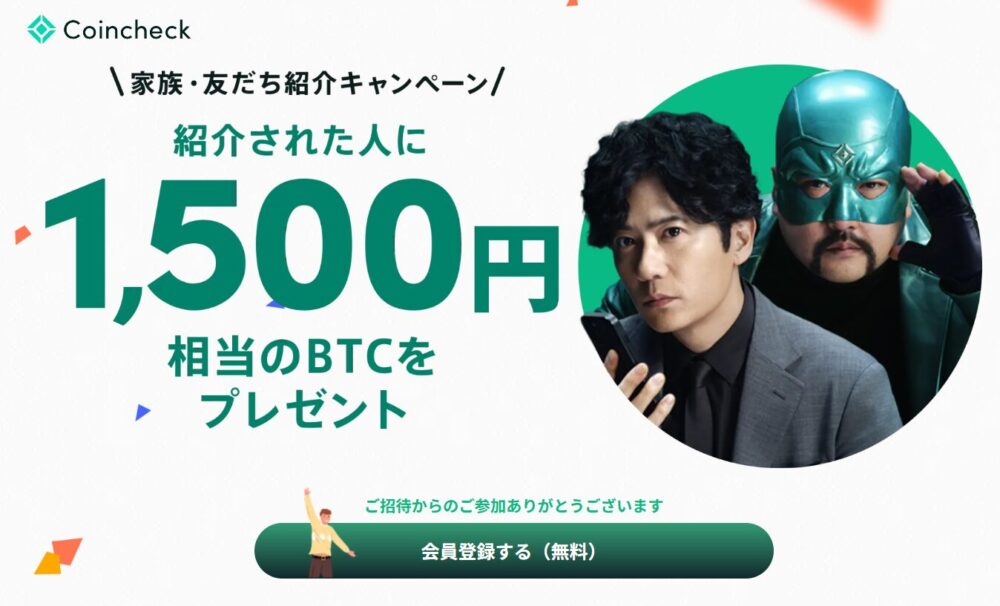
→当サイト限定!初めての「コインチェック」ご利用で1500円相当のビットコインがもらえる!
イーサリアムの発行量とEIP-1559の影響

ポイント
・EIP-1559とは?仕組みと目的
・ベースフィーの導入とバーン(焼却)メカニズム
・発行量とバーン量のバランス
・「超音波マネー」としてのイーサリアムの未来
・PoS(プルーフ・オブ・ステーク)への移行と影響
EIP-1559とは?仕組みと目的
EIP-1559(Ethereum Improvement Proposal 1559)は、2021年8月に「ロンドン・ハードフォーク」として導入されたイーサリアムの大きなアップデートの一つです。このEIP-1559によって、イーサリアムの取引手数料(ガス代)の仕組みが大幅に変更されました。
それまでのイーサリアムでは、ユーザーがマイナー(PoW時代)やバリデーター(PoS時代)に直接ガス代を支払うオークション方式でした。しかし、EIP-1559の導入により、「ベースフィー」と呼ばれる固定手数料が導入され、このベースフィーはバーン(焼却)される仕組みになりました。
つまり、EIP-1559の目的は以下の2点です。
- ガス代の安定化:ネットワーク混雑によるガス代の急騰を抑制する
- ETHの供給調整:ベースフィーのバーンによって、ETHの総供給量を抑える
この仕組みにより、イーサリアムは「インフレ通貨」から「デフレ通貨」に近づく可能性を持つようになりました。
ベースフィーの導入とバーン(焼却)メカニズム
EIP-1559では、取引ごとに「ベースフィー」と呼ばれる手数料が発生し、これはネットワークの混雑状況に応じて変動します。そして、このベースフィーはすべてバーン(焼却)されるため、ETHの供給量が減少する要因となります。
また、ユーザーは「チップ」として追加のガス代(優先手数料)を支払うことで、トランザクションの優先度を上げることができます。この「チップ」はバリデーター(PoS)への報酬となります。
この仕組みの影響で、取引が増えるほどETHのバーン量も増加し、供給量の増加を抑える効果が生まれるのです。
発行量とバーン量のバランス
EIP-1559導入後の発行量とバーン量のバランスは、以下のように変化しました。
- ETHは新規発行されるが、一部はバーンされる
- ネットワークの使用率が高まると、バーン量が発行量を上回ることがある
- 結果として、ETHの総供給量が減少する可能性がある
例えば、2022年のThe Merge(PoS移行)以降、ETHの発行ペースは大幅に減少し、バーン量が発行量を上回ることも増えました。これにより、ETHは「超音波マネー(Ultra Sound Money)」と呼ばれるようになり、デフレ資産としての価値が注目されるようになりました。
「超音波マネー」としてのイーサリアムの未来
「超音波マネー(Ultra Sound Money)」とは、ETHのバーンによって供給量が減少し、より価値が上がるという概念です。これは、発行上限があるビットコインの「デジタルゴールド」という価値の保存モデルとは異なり、ETHがネットワークの成長とともに価値を高める可能性を示唆しています。
もし今後、イーサリアム上のDAppsやNFT、DeFiの取引がさらに増えれば、ETHのバーン量も増加し、供給量が減少することでデフレ資産となる可能性があります。
PoS(プルーフ・オブ・ステーク)への移行と影響
2022年の「The Merge」により、イーサリアムはPoW(プルーフ・オブ・ワーク)からPoS(プルーフ・オブ・ステーク)へ移行しました。この変更の影響は以下のようなものがあります。
- 新規発行量の削減:PoS移行後、ETHの発行量は約90%減少
- 環境負荷の低減:PoWのマイニングが不要になり、電力消費が激減
- バーンと発行のバランス変化:取引量が増えれば、ETHの供給量が減少する可能性
特に、PoSではバリデーターに支払われる報酬がPoW時代よりも少ないため、発行量の増加が抑えられます。これにより、ETHの「デフレ資産」としての特性が強まり、長期的に価値が向上する可能性があるのです。
イーサリアムとビットコインの発行モデル比較

ポイント
・ビットコインの発行上限は?
・ハーフニングによる供給減少メカニズム
・イーサリアムの無制限発行モデルのメリット・デメリット
・価格への影響と投資戦略
ビットコインの発行上限は?
ビットコインは「デジタルゴールド」として設計されており、発行上限が2,100万枚に固定されています。これは、サトシ・ナカモトがインフレを防ぎ、希少性を持たせるために設計した仕組みです。
ビットコインは約4年ごとに「半減期(ハーフニング)」を迎え、マイナーへの報酬が半減することで新規発行量が減少していきます。最終的には2140年ごろに新規発行がゼロになり、それ以降はマイナーの収入は取引手数料のみとなります。
ハーフニングによる供給減少メカニズム
ビットコインは以下のように、新規発行量が減少する仕組みになっています。
| 半減期 | 年 | マイニング報酬(BTC) |
|---|---|---|
| 1回目 | 2012年 | 50 → 25 |
| 2回目 | 2016年 | 25 → 12.5 |
| 3回目 | 2020年 | 12.5 → 6.25 |
| 4回目 | 2024年予定 | 6.25 → 3.125 |
このように、新規発行量が減少することで、ビットコインの供給は年々少なくなり、希少性が高まる仕組みになっています。これが「ビットコインはインフレに強い」と言われる理由です。
イーサリアムの無制限発行モデルのメリット・デメリット
イーサリアムにはビットコインのような発行上限がなく、適度なインフレを維持することでネットワークの持続可能性を高める設計になっています。
メリット
- ネットワークの維持とバリデーター(PoS)への報酬を確保できる
- 取引が活発になるとバーン(焼却)による供給減少が期待できる
- PoS移行により、発行量が大幅に削減され、デフレ資産になる可能性がある
デメリット
- 供給量が一定でないため、投資家にとって不安要素となる可能性がある
- 価格の安定性がビットコインに比べて低い
- 供給管理の仕組みが変わる可能性があり、長期的な予測が難しい
価格への影響と投資戦略
ビットコインは発行上限があるため、「デジタルゴールド」としての価値が高まり、長期的な価格上昇が期待されています。一方、イーサリアムは発行上限がないものの、EIP-1559の導入やPoS移行によって供給量が減少する可能性があり、「超音波マネー(Ultra Sound Money)」としての特性が強まっています。
そのため、ビットコインは長期保有(HODL)向きの資産であり、イーサリアムはネットワークの成長とともに価格が変動しやすい投資対象と考えられます。
イーサリアムを買うなら「コインチェック」がおすすめ!
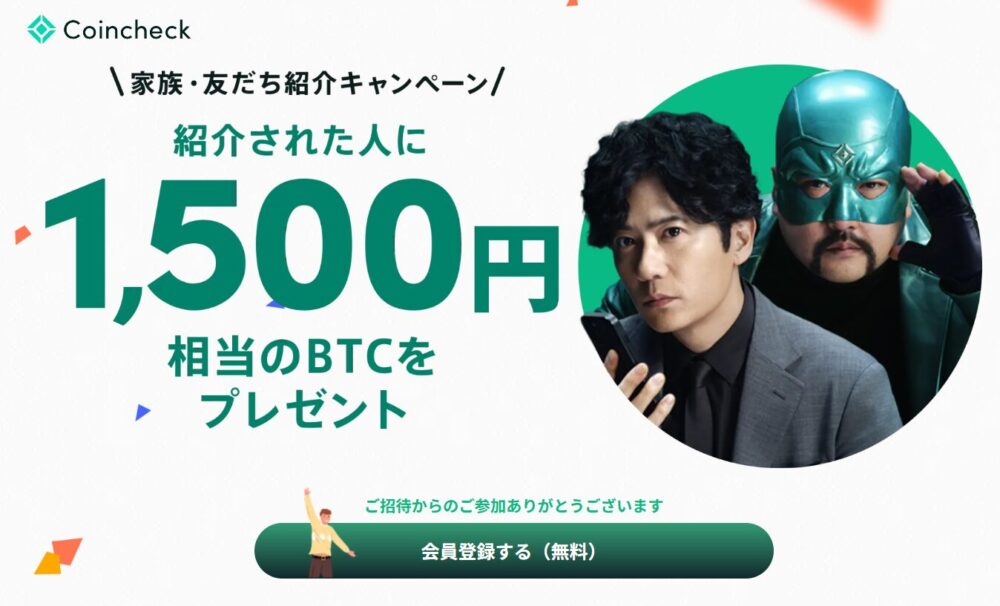
→当サイト限定!初めての「コインチェック」ご利用で1500円相当のビットコインがもらえる!
イーサリアムの未来と投資家が知っておくべきポイント

ポイント
・イーサリアム2.0とシャーディングの影響
・発行量の管理と持続可能性
・長期的な価格予測と市場動向
・ステーキング報酬と投資戦略
・イーサリアムの将来は「デフレ通貨」になるのか?
・この記事のまとめ
イーサリアム2.0とシャーディングの影響
イーサリアムは今後も進化を続けており、その中心となるのが「イーサリアム2.0」と呼ばれる大規模アップデートです。すでにPoS(プルーフ・オブ・ステーク)への移行(The Merge)は完了しましたが、次の大きなステップとして「シャーディング」が導入される予定です。
シャーディングとは、ネットワーク全体を複数の小さなブロックチェーン(シャード)に分割し、並行して処理することでスケーラビリティ(処理能力)を向上させる技術です。これにより、現在のイーサリアムが抱える「取引速度の遅さ」や「高額なガス代」といった問題が大幅に改善されると期待されています。
発行量の管理と持続可能性
イーサリアムは発行上限がないため、供給量の管理が投資家にとって重要なポイントとなります。EIP-1559の導入によりバーン(焼却)が進んでおり、PoS移行後は発行量も大幅に減少しました。
その結果、現在のイーサリアムは「発行量 < バーン量」となることもあり、ビットコインと同様に供給が減少するデフレ資産になる可能性が高まっています。今後、ネットワークの利用が増えれば増えるほどバーン量も増えるため、長期的には供給が抑制され、価格の上昇要因となるでしょう。
長期的な価格予測と市場動向
イーサリアムの価格は、ビットコインと同様に仮想通貨市場全体の動向に左右されます。しかし、以下のような要因によって、ビットコインとは異なる成長パターンを示す可能性があります。
- DeFi(分散型金融)の発展によるETHの需要増加
- NFT市場の成長とETHの活用拡大
- 企業や政府によるブロックチェーン活用の増加
- ステーキングによる供給減少と投資家の長期保有傾向
特に、イーサリアムはスマートコントラクトのプラットフォームとしての役割を持つため、Web3の成長とともに価値が高まる可能性があります。
ステーキング報酬と投資戦略
イーサリアムのPoSモデルでは、32ETHをステークすることでバリデーターとしてネットワークに参加し、報酬を得ることができます。また、個人投資家でも取引所やステーキングプールを利用すれば、少額のETHでもステーキングが可能です。
ステーキングの利回りは約4~5%とされており、長期的にETHを保有することで、価格上昇と報酬の両方を狙うことができます。そのため、短期のトレードよりも、ステーキングを活用した長期投資戦略が有効と言えるでしょう。
イーサリアムの将来は「デフレ通貨」になるのか?
現在のバーンと発行のバランスを考えると、イーサリアムは将来的にデフレ通貨となる可能性が高いです。特に、ネットワークの利用が増え、取引量が多くなるほどバーン量が増加するため、ETHの総供給量はさらに減少する可能性があります。
ただし、仮想通貨市場は変化が激しく、規制や技術の進展によって大きく影響を受けるため、慎重な分析と情報収集が必要です。
「イーサリアムに発行上限がないのはなぜ?仕組みと理由を解説!」のまとめ
イーサリアムにはビットコインとは異なり発行上限がありませんが、EIP-1559の導入やPoS移行により、供給量が抑制される仕組みが整っています。
今後の成長を考えると、以下のポイントが重要になります。
- イーサリアム2.0(シャーディング)の導入により、ネットワークのスケーラビリティが向上する
- EIP-1559のバーンメカニズムにより、供給量が減少しデフレ資産になる可能性がある
- DeFiやNFT、Web3の発展によってETHの需要が拡大する
- ステーキングによる報酬が長期保有を促進し、供給の圧縮につながる
以上の点を踏まえ、イーサリアムは「発行上限がないから価値が下がる」という単純な話ではなく、「ネットワークの成長とともに供給が管理される設計」であることが分かります。
長期的に見ると、イーサリアムは単なる仮想通貨ではなく、分散型インターネットの基盤として成長し続ける可能性を秘めています。そのため、投資を検討する際は、単なる価格の上下ではなく、技術的な進化やエコシステム全体の発展にも注目することが重要です。