広告
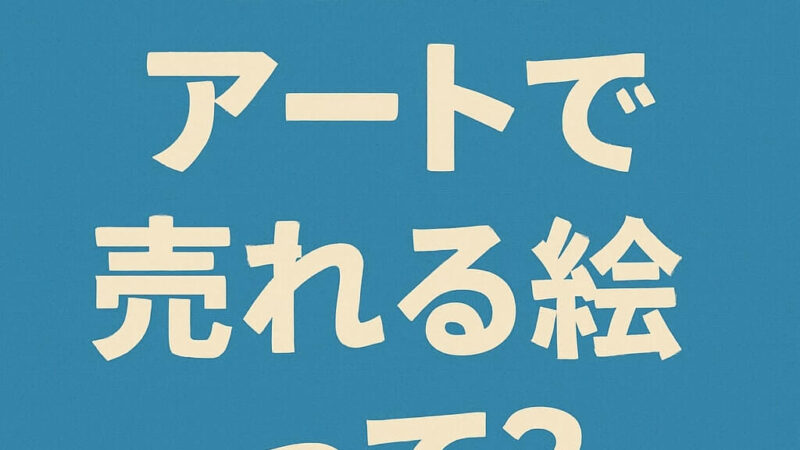
「NFTアートってもうオワコンじゃないの?」「売れないって聞いたけど、本当に稼げるの?」——そんな不安を抱えながら、NFTの世界に興味を持っている人は多いのではないでしょうか。
確かに一時の熱狂的なブームは落ち着きましたが、実は今こそが「本物のアーティスト」が活躍できるタイミング。この記事では、売れたNFTアートの事例から、実際にいくらで売れるのか、初心者でも始められる作り方まで、リアルな情報を徹底解説します。
「売れない」と言われる今だからこそ、売れる絵の描き方を知って、一歩踏み出してみませんか?
ビットコインを買うなら「コインチェック」がおすすめ!
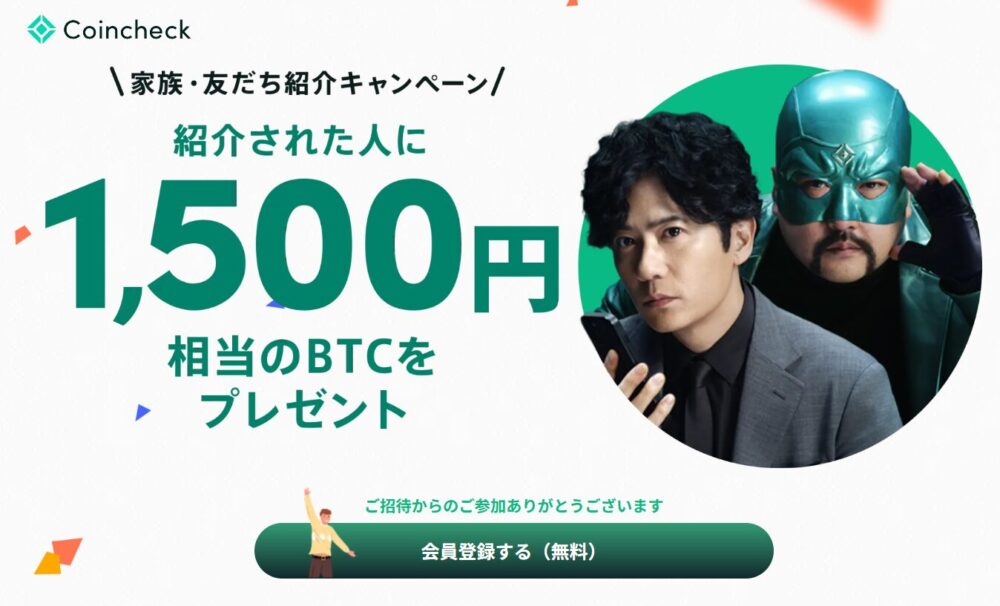
→当サイト限定!初めての「コインチェック」ご利用で1500円相当のビットコインがもらえる!
売れたNFTアートの成功事例から学ぶ「売れる絵」の特徴

ポイント
・どんなジャンルが売れているのか?
・実際に売れたNFTアートの価格帯は?
・成功アーティストのプロモーション術
・海外と日本で売れるNFTの違い
・売れた後の換金方法と注意点
どんなジャンルが売れているのか?
NFTアートで売れているジャンルには、いくつかの傾向があります。まず目立つのは「キャラクター系」です。動物や人間の顔をユニークに描いた作品はコレクション性が高く、人気を集めています。特に「PFP(プロフィール画像)系」と呼ばれるタイプは、SNSのアイコンにしやすいため売れやすい傾向があります。
次に、「ドット絵」「ピクセルアート」などの懐かしさを感じさせるスタイルも人気です。CryptoPunksなどの成功例もあり、このジャンルは今でも一定の需要があります。また、「ジェネラティブアート」と呼ばれる、プログラムで自動生成されたアートも評価されています。自分で描くというよりも、コードとアートを組み合わせた独自性が強みです。
ジャンル選びのポイントは「他の人と違うけど、理解しやすいもの」を選ぶことです。難解すぎる作品よりも、「誰かの心に刺さる要素」が入っているアートが売れやすいといえるでしょう。
実際に売れたNFTアートの価格帯は?
NFTアートは「数百円から数百万円」まで、価格の幅がとても広いです。しかし、初心者がいきなり高額で売るのは難しいのが現実です。最初は0.01ETH(約3,000円前後)で出品して徐々に実績を積み、ファンを増やしていくのが一般的な戦略です。
例えば、日本人クリエイターが描いたキャラクター系NFTが、最初は0.005ETHで販売され、コレクターの間で話題となって最終的には1ETH(数十万円)以上で取引されたというケースもあります。売れるためには「価格設定」も戦略のひとつです。
大切なのは「売れた実績」が信用になるということ。安くても1つでも売れれば、それが信頼となって次につながります。初心者は実績づくりを優先し、価格は徐々に上げる方が現実的です。
成功アーティストのプロモーション術
NFTアートで成功している人は、ただ描くだけではなく、「自分を売ること」もとても上手です。まずSNS、特にX(旧Twitter)を活用し、制作過程を発信したり、作品の世界観を語ったりしています。これによりフォロワーが増え、作品が注目されやすくなります。
また、NFTコミュニティにも積極的に参加し、他のアーティストやコレクターと交流して信頼関係を築く人も多いです。作品を出す前からファンを作っておくことで、「リリース=即売れ」の流れをつくることができます。
「アートの実力だけで勝負」は幻想です。作品の魅力と同じくらい、アーティスト本人の魅力も大切です。人柄を見せること、発信することを恐れずに行動しましょう。
海外と日本で売れるNFTの違い
日本では「可愛い」「美しい」アートが好まれますが、海外では「奇抜」「個性的」なアートの人気が高い傾向があります。たとえば、グロテスクなモンスターや社会風刺を含んだ作品が海外で売れることもよくあります。
また、海外は「プロジェクト性」を重視する傾向が強く、1枚の絵よりも「シリーズ」や「物語性」を重んじる傾向があります。反対に日本では1点物のアートも根強く評価される土壌があります。
売る相手が日本人か海外かによって、絵の方向性やプロモーションの仕方を変える必要があります。どちらの市場を狙うかを最初に決めて、戦略を立てることが成功の近道です。
売れた後の換金方法と注意点
NFTアートが売れてETH(イーサ)などの仮想通貨が手に入ったら、最終的には日本円に換金する必要があります。その際には「仮想通貨取引所」の口座が必要です。代表的な取引所としてはbitFlyer、Coincheck、GMOコインなどがあります。
注意すべきは、換金時にかかる「手数料」と「税金」です。特に税金は無視できません。NFTアートの売上も「雑所得」に分類され、確定申告が必要になります。仮に年間で20万円以上の利益が出た場合は必ず申告しましょう。
また、仮想通貨の価格変動リスクにも注意が必要です。売れた時点では高くても、換金するまでに価格が下がることもあります。売れた直後にすぐ日本円に変えておくなど、リスクを回避する工夫も大切です。
「NFTアートは売れない」と言われる理由と現実
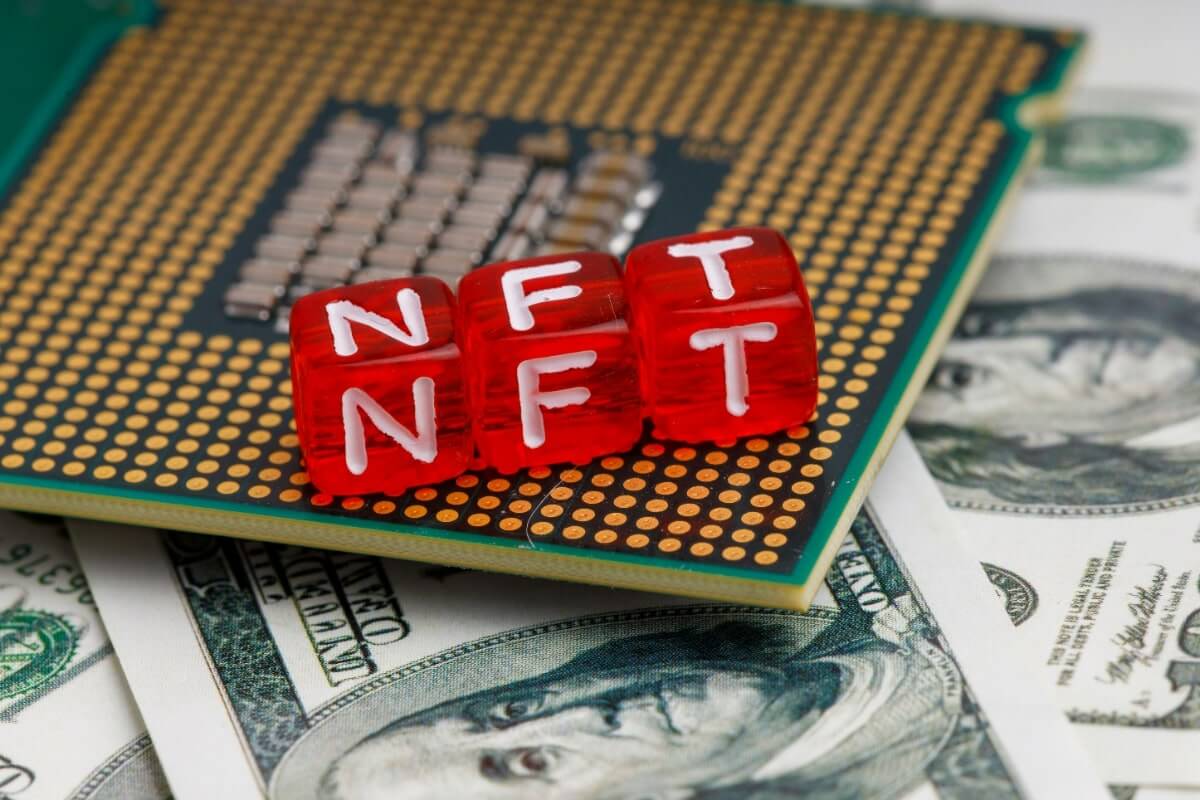
ポイント
・オワコンと言われる背景とは?
・売れないNFTアートの共通点
・「売れない」から「売れる」に変わる視点
・落とし穴になりやすい販売プラットフォーム選び
・初心者が避けるべき失敗パターン
オワコンと言われる背景とは?
NFTアートが「オワコン」と言われるようになった理由は、ブームのピークが過ぎたことが大きな要因です。2021年〜2022年頃には、NFTアートは話題になり、高額での取引がニュースになりました。しかし2023年以降、急激に市場が冷え込み、「買い手がいない」「売れない」と感じる人が増えました。
もうひとつの理由は、参入者が増えすぎたことです。誰でも簡単にNFTを出品できるようになったため、作品数が飽和状態になり、個人のアートが埋もれてしまったのです。その結果、「自分は売れなかった=NFTはオワコン」と感じる人が増え、そういった声がSNSで拡散されていった背景があります。
ただし、「市場が縮小=完全終了」ではありません。今もなお売れている人がいるのは事実であり、戦略と努力次第でチャンスは十分にあります。
売れないNFTアートの共通点
売れないNFTアートには、いくつかの共通点があります。まず「作品が雑」「魅力が伝わらない」「個性がない」という点です。単に画像を出品するだけでは、購入者の心には刺さりません。ストーリー性や意味、世界観がある作品ほど注目されやすいです。
次に「プロモーション不足」。どれだけ良い作品を描いても、見てもらえなければ意味がありません。SNSを使わずにただ出品しているだけでは、ほとんど誰の目にも止まりません。
さらに「価格設定が適切でない」ことも原因です。初心者なのに高額に設定してしまったり、無料でばらまいて価値が下がったりと、価格戦略のミスも売れない理由のひとつです。
「売れない」から「売れる」に変わる視点
「売れない」状態から抜け出すには、まず「なぜ売れないのか」を客観的に分析することが大切です。作品の質、見せ方、プロモーション、価格設定など、一度全部見直してみましょう。
そして、ただ「売れる絵を描こう」とするのではなく、「誰に買ってもらいたいのか?」という視点で考えることが重要です。ターゲットが明確になれば、その人に刺さる世界観やスタイルが見えてきます。
また、「売るまでのプロセス」も重視すべきです。出品前からSNSで作品の進捗を見せたり、完成のカウントダウンをしたりすることで、買う側の期待値を高められます。
落とし穴になりやすい販売プラットフォーム選び
NFTアートを販売するプラットフォームは多数ありますが、それぞれ特性が異なります。代表的なものにOpenSea、Foundation、Raribleなどがあります。初心者にとって使いやすいのはOpenSeaですが、出品者も多く、目立つには工夫が必要です。
一方、Foundationは審査制のため信頼性が高く、購入者も「本気のコレクター」が多い傾向があります。ただし招待制であり、参入のハードルがあります。
また、EthereumチェーンとPolygonチェーンの違いにも注意しましょう。Polygonはガス代(手数料)が安く初心者向きですが、作品の価値が低く見られることもあります。
プラットフォーム選びを間違えると、どんなに良い作品でも売れないことがあります。目的や作品の方向性に合った場所を選びましょう。
初心者が避けるべき失敗パターン
NFTアート初心者がやりがちな失敗には、以下のようなものがあります:
- 「とりあえず描いて出品」して終わり
- 価格設定が感覚的で戦略がない
- 宣伝を全くせずに放置
- 海外の動向を無視して日本だけに固執
- 他人の成功と比較して焦る
これらはすべて、「準備不足」や「情報不足」が原因です。NFTはアートであると同時に、ビジネスでもあります。「売れるための流れ」を理解して、ひとつひとつ丁寧に進める姿勢が成功への第一歩です。
ビットコインを買うなら「コインチェック」がおすすめ!
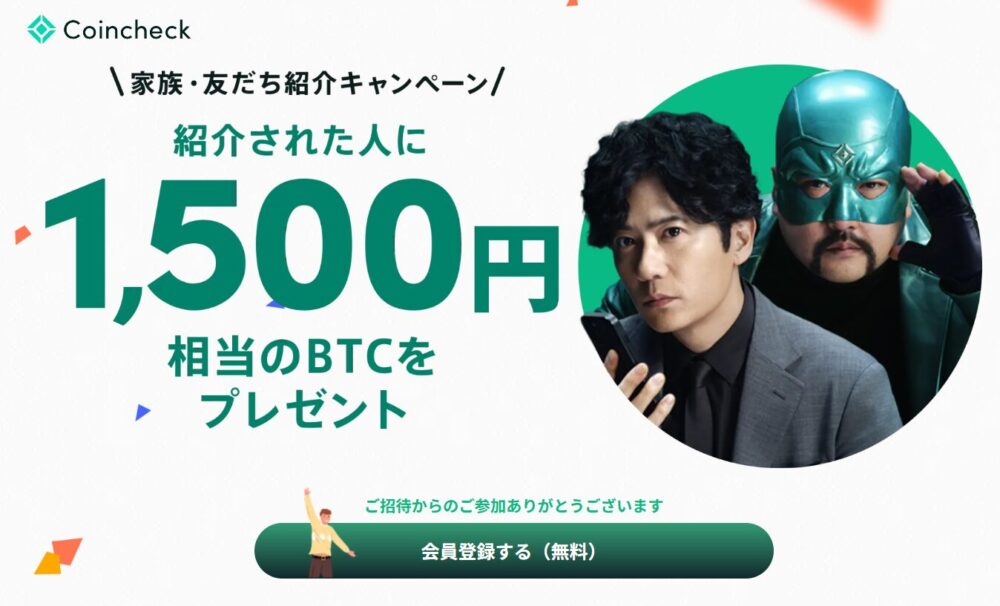
→当サイト限定!初めての「コインチェック」ご利用で1500円相当のビットコインがもらえる!
今の時代いくらで売れる?NFTアートの市場価格とトレンド分析

ポイント
・2025年現在のNFTアート市場の動向
・実際の販売価格とその幅
・人気の価格帯とは?
・安く売るべき?高く設定するべき?
・販売価格を上げるための付加価値戦略
2025年現在のNFTアート市場の動向
2025年現在、NFTアート市場は2021年のバブル期ほどの熱狂はないものの、安定した市場として成熟しつつあります。投機的な購入が減り、「本当に欲しいアートを買う」という本来のアート市場に近い動きが目立つようになりました。
また、大手企業や有名ブランドのNFT参入が進んだことで、一般層の認知も広がっています。その一方で、個人アーティストの作品は「ブランド化」や「ストーリー性」がないと目立ちにくくなっています。
プラットフォーム側も質の高い作品を優先表示するアルゴリズムに変わってきており、「ただ出せば売れる」時代は終わりました。とはいえ、作品やアーティストの魅力をしっかり伝えられる人にとっては、むしろチャンスが広がっているともいえます。
実際の販売価格とその幅
NFTアートの販売価格には大きな幅があります。以下のように分類できます:
| 分類 | 販売価格帯 | 特徴 |
|---|---|---|
| 初心者 | 0.001〜0.02 ETH | 実績作りやファン獲得を重視 |
| 中堅クリエイター | 0.03〜0.3 ETH | コレクターからの信頼あり |
| 有名プロジェクト | 0.5〜10 ETH | ブランド化されたシリーズ |
| 特殊事例 | 10 ETH以上 | 有名人・コラボなど |
1ETHが現在約35万円とすると、初心者は3,000円〜5,000円程度からスタートするのが一般的です。いきなり高額を狙うよりも、まずは「売れる」経験を積むことが大切です。
人気の価格帯とは?
現在、最も売れやすいのは「0.01〜0.05ETH(約3,000〜18,000円)」の価格帯です。このあたりの価格であれば、コレクターも「試しに買ってみようかな」と思いやすく、購入のハードルが低くなります。
高額なNFTは購入者が慎重になるため、何かしらの「買う理由」が必要になります。例えば、有名人とのコラボだったり、リアルイベントへの招待権がついていたりなどの付加価値が求められます。
逆に無料や0.001ETH(約300円)以下だと、逆に「安すぎて価値がなさそう」と思われることもあるので注意が必要です。適正価格を見極めましょう。
安く売るべき?高く設定するべき?
価格設定は「実績がないうちは安く、実績ができたら少しずつ上げる」が基本です。初期段階では「この人の作品を買う理由」が明確でないため、高く設定しても売れません。
一方、実績やフォロワーが増えれば「その人の作品なら欲しい」という需要が生まれます。そうなったら価格を上げても売れるようになります。
また、「1点ものは高め」「コレクションは安め」といった戦略も有効です。シリーズものは数を売ることを目的に価格を抑え、一点物のアートには高めの価値をつけることで、アーティストとしての幅を広げられます。
販売価格を上げるための付加価値戦略
販売価格を上げるには、単なる絵以上の「価値」をつけることが重要です。以下のような付加価値が有効です:
- ストーリー性:キャラクターの背景や世界観を語る
- 購入者特典:作品購入者に限定アイテムや情報を提供
- 限定性:「10点限り」などの希少性をアピール
- リアル連動:NFT購入者に原画を送る、展示会へ招待する
- コレクション化:シリーズ作品でコレクション性を高める
このように、「作品+α」の要素を工夫することで、価格を高くしても納得してもらいやすくなります。ただし、内容と価格が釣り合っていないと逆効果になるため、バランスを意識することが大切です。
売れるNFTアートの作り方とは?初心者からでもできる作品制作のステップ

ポイント
・必要な機材とソフト
・売れるジャンルとモチーフ選び
・「売れる絵」を描くコツと構図
・キャラや世界観の設計方法
・ミント(NFT化)から出品までの流れ
必要な機材とソフト
NFTアートを始めるのに、高価な道具は必ずしも必要ではありません。基本的には「パソコン」と「ペイントソフト」があればOKです。具体的には、以下のようなツールが人気です:
- iPad + Procreate:直感的に描けて初心者にも人気
- PC + Photoshop:細かい編集が可能でプロ向き
- Clip Studio Paint:マンガやイラスト制作に最適
- Blender(3D):3Dアートを作るなら必須
パソコンやiPadは、5万円〜10万円程度のスペックでも十分に使えます。また、描いた後にNFTとして出品するための「メタマスク(MetaMask)」というウォレットアプリと、NFTマーケット(OpenSeaなど)への登録も必要です。これらはすべて無料で始められます。
売れるジャンルとモチーフ選び
売れるNFTアートには、「世界観」や「物語性」が求められます。ただキレイに描かれた絵だけでなく、「誰に刺さるか」「どう感じてもらいたいか」が大切です。
ジャンルで言うと、以下のようなモチーフが人気です:
- 動物キャラ(ネコ、クマ、鳥など)
- 幻想的な風景や宇宙モチーフ
- ピクセルアートやドット絵
- 日本アニメ風イラスト
- アイコン用PFPキャラ
自分が描いていて楽しいテーマと、需要があるジャンルのバランスを取るのがコツです。「こんなの自分しか描けない」と思えるモチーフがあると、アートの価値も上がります。
「売れる絵」を描くコツと構図
売れる絵には「パッと見て分かる魅力」があります。構図で言えば、顔が大きく中央にある「バストアップ」や、シンプルな背景でキャラを目立たせるスタイルが効果的です。
以下のコツも意識してみてください:
- 色使いは3〜4色にまとめてインパクトを出す
- 目を引くキャッチーな表情やポーズを取り入れる
- 余白を意識し、スマホでも見やすい構図にする
- 1枚の絵でストーリーが想像できるようにする
また、NFTはサムネイルが重要です。スマホの小さな画面でも「これ欲しい!」と思われるようなビジュアルを意識して描くことが大切です。
キャラや世界観の設計方法
「キャラの魅力=売れる力」と言っても過言ではありません。特にコレクション系のNFTでは、「このキャラにはこんな背景がある」「この世界にはこんなルールがある」といった設定がしっかりしていると、ファンがつきやすくなります。
世界観を設計するには、以下のような要素を整理するとよいでしょう:
- キャラの性格や特徴(例:怒りっぽいが心優しいネコ)
- 世界の舞台(例:空飛ぶ島で暮らす生き物たち)
- ルールや文化(例:色ごとにランクが分かれる社会)
- シリーズ名やタイトル(例:「Sky Cats Collection」)
このようなバックグラウンドを作品に込めることで、ただの「デジタル絵」ではなく、「物語あるアート」として認識され、コレクターの心に響きます。
ミント(NFT化)から出品までの流れ
作品が完成したら、いよいよNFTとして出品です。以下の手順で進めます:
- MetaMaskをインストールし、ウォレットを作成
- OpenSeaなどのNFTマーケットに登録
- 作品をアップロード
- 作品の名前・説明・価格を設定
- ミント(NFT化)を実行し出品完了
現在では「ガス代無料(ガスレス)」で出品できるPolygonチェーンを使う方法が初心者に人気です。ETHチェーンは手数料が高いため、最初はPolygonで始めるのが安心です。
出品後は必ずSNSで宣伝し、作品の魅力を伝えていきましょう。どれだけ素晴らしい作品でも、見つけてもらえなければ売れません。作品を「育てる」意識も大切です。
ビットコインを買うなら「コインチェック」がおすすめ!
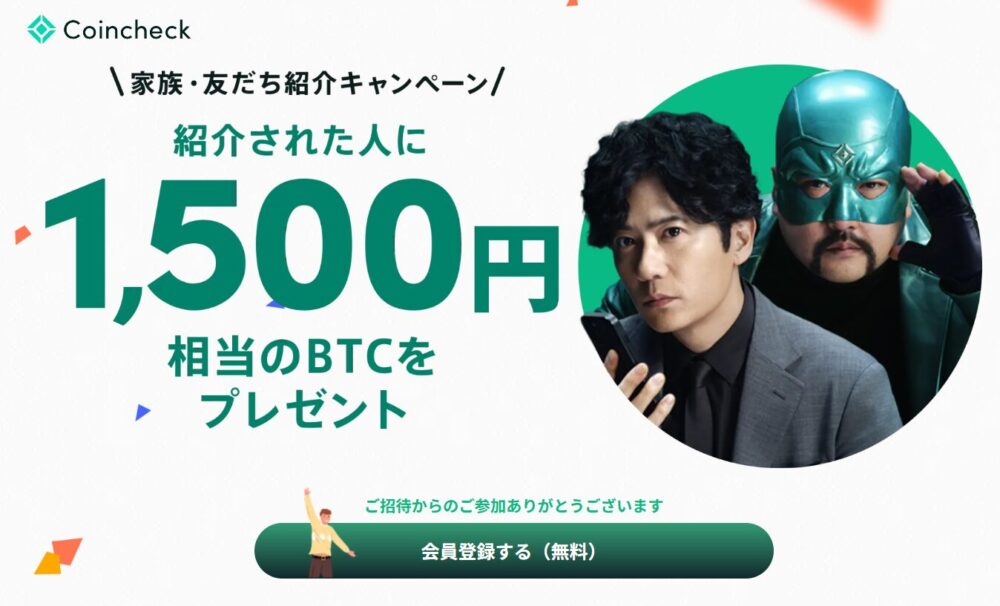
→当サイト限定!初めての「コインチェック」ご利用で1500円相当のビットコインがもらえる!
「NFTアートには手を出すな」は本当か?やめたほうがいい人・向いている人の違い
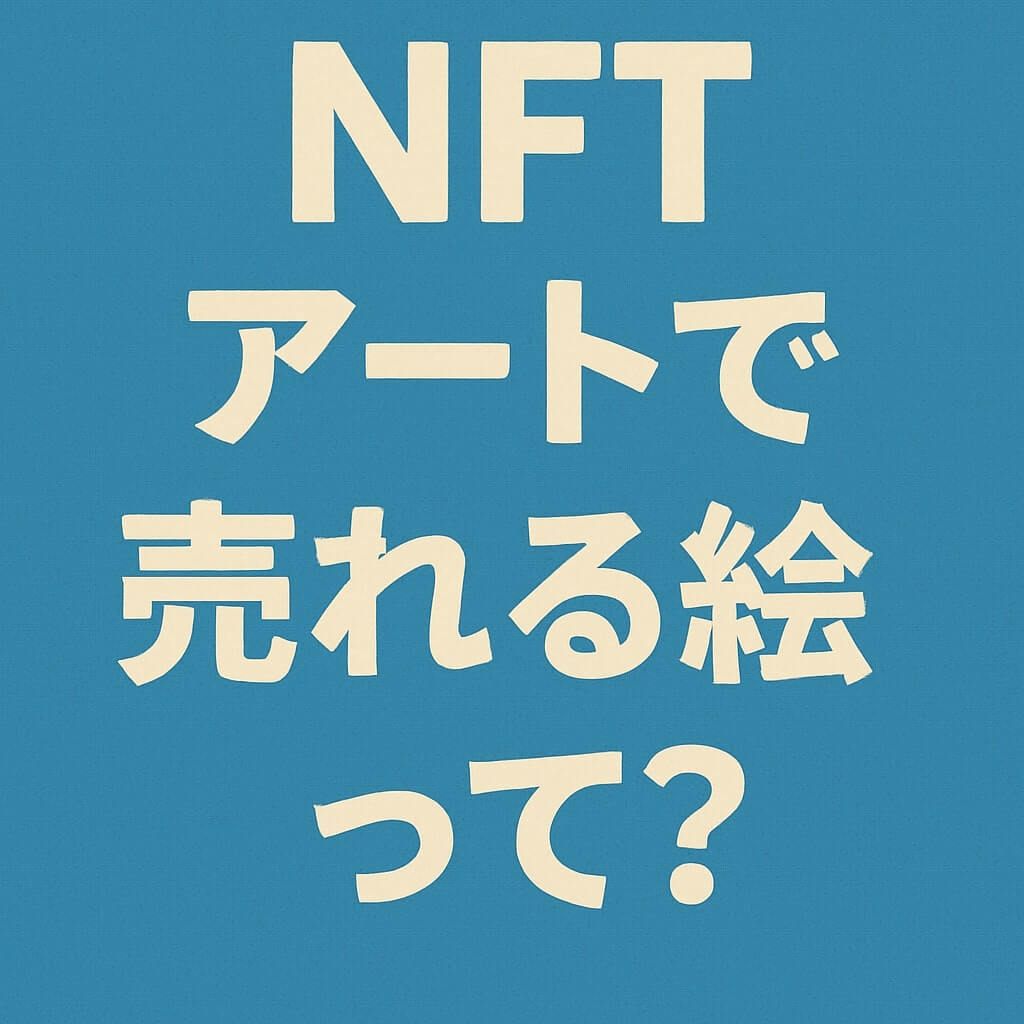
ポイント
・向いていない人の特徴とは?
・向いている人のマインドセット
・継続できる人と挫折する人の分かれ道
・NFTより他の手段が合う場合とは?
・成功者たちが語るメリットとデメリット
・この記事のまとめ
向いていない人の特徴とは?
「NFTアートには手を出すな」という意見もありますが、実際に向いていない人も確かに存在します。たとえば、以下のような人は注意が必要です:
- 楽してすぐに稼ぎたいと思っている人
- SNSが苦手で発信が一切できない人
- 継続ができず、すぐにあきらめてしまう人
- 人の成功と比較して落ち込みやすい人
- 仮想通貨やパソコン操作が極端に苦手な人
NFTアートは、絵を描くだけでなく、「発信力」「継続力」「リスク管理」が必要な分野です。アートが上手でも、それだけでは売れないことも多く、根気強く試行錯誤できるかが鍵になります。
また、価格の上下や市場の変化に一喜一憂するような人にとっては、精神的な負担も大きいかもしれません。
向いている人のマインドセット
逆に、NFTアートに向いている人はどんな人でしょうか?それは「自分の世界観を人に伝えるのが好きな人」です。具体的には以下のような特性を持つ人です:
- 人に何かを届けたい、見てもらいたいという気持ちが強い
- 新しいことにワクワクできる人
- アートとビジネスの両方に興味がある
- ファンを育てることに喜びを感じられる
- 自分の作品をブランドとして育てたい人
NFTアートは「自分の世界観を形にするプラットフォーム」です。発信すればするほど、そこに共感したファンが集まってきます。そして、その人たちと一緒に世界を作っていけるのが大きな魅力です。
継続できる人と挫折する人の分かれ道
NFTアートの世界で「続けられる人」と「やめてしまう人」の違いは、売れる・売れないではなく「行動できるかどうか」にあります。
継続できる人の特徴:
- 小さな反応や売上でもポジティブに受け止める
- 他人の成功を分析して自分に活かす
- 失敗しても記録を残し、改善を続ける
- 自分のペースでコツコツ進める
挫折する人の特徴:
- すぐに結果が出ないとモチベーションが下がる
- SNSで他人の売上ばかり気にして落ち込む
- 1つの失敗で「自分には向いていない」と決めつける
- 行動せずに情報ばかり集める
結果を急ぐよりも、「まずは1作品を完成させる」ことがスタートラインです。売れるかどうかはその後の話で、最初は「作ること」「発信すること」に喜びを感じられるかが鍵です。
NFTより他の手段が合う場合とは?
NFTアートは魅力的な手段ですが、すべての人に最適というわけではありません。以下のような人には、他の手段が向いている場合もあります。
- SNSを使いたくない人 → LINEスタンプ販売やBOOTHなどのストア型
- 仮想通貨が不安な人 → イラストのコミッションやnoteでの販売
- 現実での活動が得意な人 → 展示会やハンドメイドイベントでの販売
- 定期収入を望む人 → スキルシェア系サービス(ココナラなど)
NFTはあくまで「手段のひとつ」です。自分の作品を届けるには、もっとシンプルで合っている方法が他にもあるかもしれません。大事なのは、「自分に合った方法で続けられるかどうか」です。
成功者たちが語るメリットとデメリット
NFTアートで成功している人たちは、その魅力と現実を冷静に語っています。以下は実際によく聞かれる声です。
メリット
- 世界中の人に自分のアートを届けられる
- 作品に「所有」という新しい価値がつく
- コレクターと長期的な関係が築ける
- 自分のブランドが育つ実感がある
デメリット
- 価格の変動や税金処理などの知識が必要
- 市場のトレンドに左右されやすい
- 偽物や盗作への対策も必要
- 売れない時期のメンタル管理が大変
成功者も、簡単にうまくいったわけではなく、多くの試行錯誤と時間をかけています。そのうえで「それでもやって良かった」と思える人が、NFTアートに向いていると言えるでしょう。
「NFTアートで売れる絵って?【売れる絵】を描いて換金するための全戦略」のまとめ
NFTアートは一時のブームから落ち着きを見せ、「売れない」と感じる人も増えてきました。しかし、実際には今も「売れているアーティスト」は存在しており、そこには明確な戦略と行動があります。この記事では、売れるために必要な要素を5つの視点から解説しました。
- 売れるアートには共通するジャンルや魅せ方があること
- 売れないと言われる現実の中にも成功する方法があること
- 市場価格や価格帯には戦略的な設定が求められること
- 誰でも始められる制作ステップと発信の重要性
- 自分にNFTが合っているか見極めるマインドの持ち方
NFTアートは簡単な道ではありませんが、「自分の世界観を発信したい」「誰かに届けたい」という強い想いがあれば、売れる可能性は十分にあります。
すぐに結果を出すことよりも、まずは描き、発信し、続けることが何より大切です。「NFTアートには手を出すな」と言われる時代だからこそ、本気で向き合う人が評価されるチャンスでもあるのです。