広告
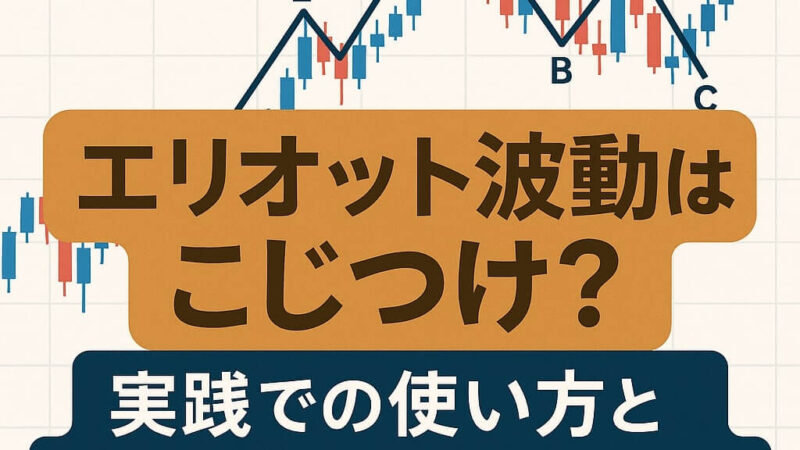
「エリオット波動って、なんかこじつけっぽくない?」
そう感じたことがある人は多いのではないでしょうか?
相場の動きを「波」に分類するエリオット波動理論。チャートを数えたり、波を判断したりと難しそうに見える一方で、今も多くのトレーダーがこの手法を実践しています。
本記事では、「こじつけ」と言われる理由から始まり、実際の使い方やだましへの対応、実践での活用ポイントまでを、わかりやすく丁寧に解説します。エリオット波動の本質を知ることで、あなたのトレードに新しい視点が加わるはずです。
エリオット波動はこじつけなのか?本質を考える
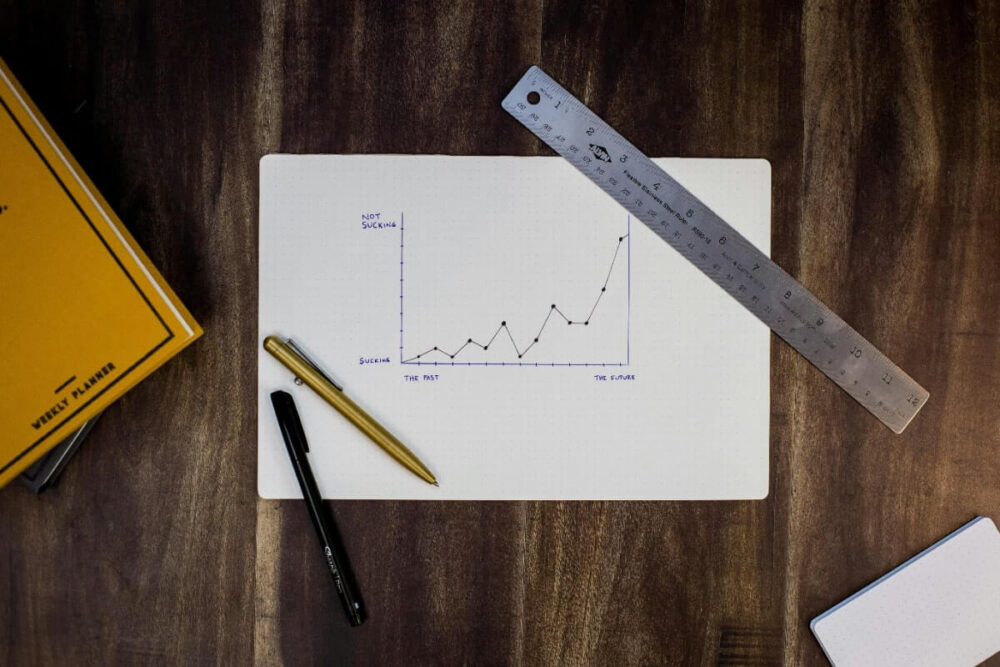
ポイント
・エリオット波動が「こじつけ」と言われる理由
・相場分析の主観と客観の違い
・歴史的背景と相場心理の関係
・チャートパターンはすべて“こじつけ”なのか?
・なぜそれでもトレーダーに支持されるのか?
エリオット波動が「こじつけ」と言われる理由
エリオット波動理論は、相場の値動きを「5つの推進波と3つの調整波」に分けて分析する理論です。ところがこの理論に対して、「後付けじゃないの?」「こじつけっぽい」という批判がよくあります。なぜそう言われてしまうのか? それは、波のカウントが見る人によって異なることが多く、明確な正解が存在しないからです。
たとえば、ある人は「これが第3波だ」と主張していても、別の人は「それはまだ第1波だ」と解釈していることもあります。このように、エリオット波動は“主観的な判断”が多分に入るため、見る人によって全く違う解釈になることが頻繁にあります。さらに、過去チャートではきれいに説明できても、リアルタイムではなかなか当てはまらない場面も多いため、「これはただのこじつけでは?」と思われるのも無理はないのです。
しかしそれは、エリオット波動に限ったことではありません。ほとんどのテクニカル分析、たとえばダブルボトムやヘッドアンドショルダーといったチャートパターンも、結果論で“当たっていた”と解釈されるケースが多く、ある種のこじつけであるとも言えます。
重要なのは、「こじつけ」のように見えるものの中に、一定のパターンや規則性を見出す力です。エリオット波動は確かに万能ではありませんが、「相場はランダムでありながらも人の心理が反映される」という視点で見ると、波動の中にある一定のリズムや繰り返しは決して無視できるものではありません。
つまり、「こじつけ」と感じるのは、まだ本質を掴み切れていない状態とも言えます。きちんと学び、検証を重ねたうえで初めて、その奥深さや使い所が見えてくるのです。
相場分析の主観と客観の違い
相場分析には「主観」と「客観」のバランスが求められます。エリオット波動は、チャートを一定の法則で読み解こうとする理論ですが、実際にカウントしていく作業は非常に主観的です。これが「正しい波の数え方だ!」と断言できるケースはまれで、多くの場合は仮説を立てながら柔軟に修正していく必要があります。
この主観的な判断が多く求められるからこそ、エリオット波動は“こじつけっぽい”と言われがちです。しかし逆に言えば、自分なりのルールやフィルターを作ることで、主観的な判断に一定の客観性を持たせることも可能です。たとえば、「第3波は必ず第1波の1.618倍以上を目安にする」「第2波は38.2〜61.8%の調整に収まると仮定する」といった具体的な基準を設ければ、波のカウントにも一貫性が出てきます。
また、主観的な判断があるからこそ、相場の“今”を見極める能力も養われます。常に同じパターンになるわけではない相場の中で、「今のチャートはどう見えるか?」を考え続けることで、自分なりの判断基準が身についていくのです。
つまり、エリオット波動は完全に客観的なツールではありませんが、主観に頼りすぎない工夫を加えることで、より再現性のある分析手法へと変えることができます。そのプロセスを通して、トレーダーとしてのスキルも確実に磨かれていくのです。
歴史的背景と相場心理の関係
エリオット波動は1930年代にラルフ・ネルソン・エリオットによって提唱されました。彼は株式市場の長期チャートを分析し、相場には一定の周期性があることに気づきました。特に彼が注目したのは、人間の感情や群集心理が相場に与える影響です。
上昇トレンドで多くの人が楽観的になり、下降トレンドでは悲観的になる。その集団的な感情の波が、一定のリズムでチャート上に現れる。エリオットはそれを「波動」として表現し、5波の推進と3波の調整という形にまとめました。
この考え方は、単なるテクニカル分析にとどまらず、心理学的な側面を強く含んでいます。つまり、相場を動かすのは経済指標だけでなく、人々の「恐怖」や「欲望」なのです。エリオット波動の本質は、そうした人間心理の繰り返しに注目したところにあります。
現代のように情報があふれ、AIやアルゴリズムが市場を動かしている時代でも、最終的に注文を出すのは人間です。だからこそ、感情の揺れが今でもチャートに波として現れるのです。このように、エリオット波動は決して古臭い理論ではなく、今でも相場心理を読み解く重要なツールとして活用できるのです。
チャートパターンはすべて“こじつけ”なのか?
「ヘッドアンドショルダー」「ダブルトップ」「ペナント」など、テクニカル分析でよく使われるチャートパターンも、実は厳密にいえば“こじつけ”と見なせる部分があります。というのも、どのパターンも完璧な形で現れるわけではなく、多少のズレや曖昧さを許容しながら解釈しているからです。
たとえば、きれいなダブルトップを狙ってエントリーしたのに、実は片方の山が少し高かったり、ネックラインをちょっと割ったあとすぐ戻ったり…。そういった例は日常茶飯事です。だからといって「使えない」と切り捨てるのはもったいない話です。重要なのは、チャートパターンが示す心理状態や市場の動きの流れを読み取ることにあります。
エリオット波動も同じで、「この波が絶対に第3波」と断定するのではなく、「このあたりに第3波が発生していそうだ」と仮説を立て、行動を組み立てることが求められます。多少のズレや誤差は当たり前で、それを許容しながらトレードの精度を高めていく姿勢が大切なのです。
なぜそれでもトレーダーに支持されるのか?
エリオット波動は「難しい」「再現性が低い」と言われながらも、なぜ今でも多くのトレーダーに支持され続けているのでしょうか? それは一言で言えば、「市場の流れを大局的に掴むことができる」からです。
多くのテクニカル指標は現在の価格に基づいて瞬間的な判断を求めますが、エリオット波動は「今が全体のどのフェーズにあるのか?」という視点で市場を読み解くことができます。たとえば「第3波の中の小波動である第5波」というように、マルチレベルで分析することで、単なる短期のブレに惑わされずに済みます。
また、エリオット波動を長年研究・実践しているプロトレーダーたちは、その再現性を高めるために独自のルールや補助ツールを使って波動を読み解いています。誰でもすぐに使いこなせるものではありませんが、学びを深めることでトレードスキルそのものが確実に磨かれる手法であることも魅力です。
エリオット波動の実践例から学ぶ使い方

ポイント
・トレンドの5波と調整の3波の基本について
・実際のチャートで読み解く波の形
・フィボナッチとの組み合わせで精度アップ!
・実践で意識すべき3つのポイント
・相場ごとに違う“波の個性”に対応する方法
トレンドの5波と調整の3波の基本について
エリオット波動の基礎となるのが、「5波動の推進」と「3波動の調整」です。まずはこの基本構造をしっかり理解することが重要です。相場が上昇トレンドであれば、価格は1→2→3→4→5という順に推進し、その後A→B→Cと3つの調整波を描いて反落します。
この波の動きには法則性があり、第3波はしばしば最も強く、長い動きになります。初心者が最も狙いやすい波がこの第3波だと言われています。なぜなら、多くの市場参加者がトレンドを意識し始め、価格が加速するタイミングだからです。
一方で、第2波と第4波は調整の波で、いったんの押しや戻しが入ります。これを見誤ると「もうトレンドが終わった」と錯覚してしまうこともありますが、波動理論を理解していれば「これは第2波の押しだな」と冷静に捉えることができます。
調整波も、A→B→Cと3波構造で動くのが一般的です。特にこの調整波が終わるポイントを見極めることで、第3波や新たなトレンドの始まりをとらえることが可能になります。
波の形をしっかり理解し、現在地を判断することが、エリオット波動の活用において最も基本であり重要な第一歩です。
実際のチャートで読み解く波の形
理論だけではなく、実際のチャートを見ながら波を読み解く力も必要です。たとえばドル円や日経平均のようなメジャーな銘柄では、エリオット波動が比較的きれいに出やすいとされています。実際の相場では、チャート上の高値と安値を順に追いながら「今は第何波か?」という仮説を立てていきます。
ここで大事なのは、すべてを一発で正確にカウントしようとしないことです。波のカウントはあくまで“仮説”であり、相場が動くにつれて見直していく必要があります。たとえば、「これが第3波だと思っていたけど、どうやらまだ第1波だったらしい」と修正することも珍しくありません。
さらに、チャートにはノイズやダマしの動きも多く含まれています。そのため、1時間足だけで判断するのではなく、日足や4時間足など複数の時間軸を見比べるマルチタイム分析も効果的です。上位足での波の流れを把握し、下位足でエントリーポイントを絞るという使い方が実践的です。
理論と実チャートのすり合わせを繰り返すことで、波の読み方がどんどん磨かれていきます。
フィボナッチとの組み合わせで精度アップ!
エリオット波動を実践する上で、多くのトレーダーが活用しているのが「フィボナッチリトレースメント」です。これは、価格がどこまで押し戻されるかを予測するためのツールで、エリオット波動と非常に相性が良いとされています。
たとえば第2波の押しでは、第1波の始点から終点にフィボナッチを引くことで、38.2%、50%、61.8%といった水準が意識されやすいとされています。この中でも61.8%は「黄金比率」として特に注目されており、ここで反発して第3波へと発展するケースがよく見られます。
また、第3波の目標値もフィボナッチで推測することができます。一般的には、第1波の1.618倍の価格を目標とするケースが多く、この比率を超えるような勢いのある動きは「本物の第3波」と判断する手助けになります。
フィボナッチを使うことで、波の“終わり”や“始まり”の予測がしやすくなり、エリオット波動の精度がぐっと上がります。理論だけでなく、ツールとの連携も活用することで、より実践的なトレードが可能になります。
実践で意識すべき3つのポイント
エリオット波動を実際のトレードで使う場合、以下の3つのポイントを意識することが大切です。
- 常に仮説であることを忘れない
波のカウントは完璧ではありません。「おそらく今は第3波だろう」というように、仮説として捉えることが大切です。 - 損切りラインを明確にする
エリオット波動は当たれば大きなリターンが期待できますが、間違うことも多いです。そのため、損切りポイントをきちんと設定し、分析が外れたらすぐに撤退する姿勢が求められます。 - 複数の時間軸で確認する
日足で見た波と、1時間足で見た波では形が全く違って見えることもあります。マルチタイムでのチェックを怠らないことで、判断の精度が上がります。
これらを意識することで、実践でのエリオット波動の使い方がより安定してきます。
相場ごとに違う“波の個性”に対応する方法
相場には“個性”があります。株式、為替、仮想通貨など、対象となる市場によって値動きの癖やボラティリティが異なります。当然、それにともなって現れる波の形にも違いが出てきます。
たとえば、仮想通貨は非常にボラティリティが高いため、波が急激で複雑になる傾向があります。一方で為替相場は比較的安定しており、きれいな5-3構造が出やすいという特徴があります。
また、ニュースや経済指標などの外的要因も、波の形に影響を与えます。そうした変動要素を無視して波を数えても、意味のない分析になってしまう可能性があります。だからこそ、波の個性に柔軟に対応する観察力と適応力が必要です。
最終的には「この通貨ペアのこの時間軸では、このような波が出やすい」という自分なりのデータを蓄積していくことが、実践での勝率を上げる鍵になります。
エリオット波動の“だまし”に要注意!

ポイント
・間違いやすい波のカウントパターン
・“だまし”が起こる3つの典型的パターン
・トレードにおける損切りと撤退の重要性
・自分の分析を過信しない考え方
・“だましを活かす”逆張りのヒント
間違いやすい波のカウントパターン
エリオット波動を使ううえで最も多いミスのひとつが、波の数え間違いです。特に初心者は「これは明らかに第3波だ!」と信じてエントリーしても、実は第C波の反発だった、なんてこともよくあります。こうした誤認は、“だまし”に直結する大きな要因です。
間違いやすいのは、推進波と調整波が混在する場面や、複雑な調整波(ダブルジグザグやトライアングル)に遭遇したときです。たとえば、ABCの調整波だと思っていたものが、実はより大きな波の一部であったり、あるいは延長された第5波だったということも珍しくありません。
これを防ぐには、カウントする際のルールを自分なりに明確にし、可能であれば1つの仮説に固執せず、複数のパターンを並行して考える「シナリオ分岐」の習慣をつけることが重要です。つまり、「この形は第3波に見えるけど、違うパターンもありえるな」と冷静に複数の選択肢を持つことで、だましを回避する確率がぐっと上がります。
“だまし”が起こる3つの典型的パターン
エリオット波動における“だまし”には、ある程度パターンがあります。ここでは特にトレーダーがひっかかりやすい3つのケースを紹介します。
- 誤認第3波
多くの人が「強い上昇=第3波」と決めつけがちですが、実際には第C波の調整反発であることも多く、これに飛びつくと高値づかみになることがあります。 - 第4波のフェイクブレイク
第4波はレンジになりやすく、フェイクアウト(だましのブレイク)がよく起こります。安易にブレイク狙いで飛び込むと、すぐに反転して損失になるケースが多発します。 - トライアングルの誤解
トライアングル(三角持ち合い)も一見するとブレイクの兆しに見えますが、実際はその後の大きな動きの“前の静けさ”だったりします。中途半端な場所でポジションを持つと、すぐに逆方向へ持っていかれるリスクが高いです。
こうしただましのパターンを知っておくことは、避けるための第一歩です。
トレードにおける損切りと撤退の重要性
どれだけ分析をしても、100%正確に波を当てることはできません。だからこそ大事なのが「損切り」の判断です。エリオット波動においても、波が想定と違った方向に進んだ場合、潔く撤退する姿勢が勝ち残る鍵となります。
損切りポイントは、自分の波動カウントが間違っていたと判断できる明確なレベルに設定するのが理想です。たとえば、「この波が第2波だとすると、始点を割ったらそれは第3波ではあり得ない」というように、波動の理論に基づいた損切りポイントを設定することで、論理的な撤退が可能になります。
また、損切りを躊躇していると、「まだ戻るかも」「一時的な調整だろう」といった希望的観測に陥り、結果的に損失を膨らませてしまいます。特にエリオット波動は長いトレンドを読む分析なので、間違ったまま長期間保有するリスクも大きくなります。
損切りを前提とした計画的なトレードこそが、安定した収益をもたらすのです。
自分の分析を過信しない考え方
エリオット波動をある程度理解してくると、自分の波動カウントに自信が出てきます。しかし、この“自信”が過信に変わった瞬間から、トレードは危険になります。自分の分析が正しいと信じすぎて、相場の変化に対応できなくなるのです。
相場は常に変動し続けるもので、過去にうまくいったパターンが今回も機能するとは限りません。とくにエリオット波動は相場全体の構造をとらえる分析なので、仮説が間違っている場合には早めに修正する柔軟性が求められます。
「自分が正しい」と思い込むよりも、「間違っているかもしれないから、常に確認する」という姿勢が重要です。そのためには、分析ノートをつけたり、定期的に自分のトレードを振り返るなど、第三者の目線で見直す習慣をつけることが効果的です。
自分を信じすぎず、常に検証し続ける姿勢こそ、長く生き残るトレーダーの必須条件です。
“だましを活かす”逆張りのヒント
一見すると“だまし”の動きも、うまく使えばチャンスに変えることができます。たとえば、多くの人がブレイクだと思って飛び乗ったあとに反転する動き…これは「逆張り」のチャンスです。特にレンジの終盤や、明らかにオーバーシュートした場面では、逆張りの戦略が有効になることがあります。
その際に活用できるのが、フィボナッチやサポレジラインです。だましが起きた直後に反発する場所が、ちょうど61.8%のフィボナッチラインだった…なんてケースはよくあります。こうした場所で逆張りを狙えば、リスクを限定しながらリターンを最大化できます。
もちろん、逆張りはリスクも高いため、損切り設定はより厳密に行う必要があります。しかし、相場の“だまし”を単なるミスとして片付けず、「なぜそうなったのか?」と分析していくことで、逆張りのタイミングも見えるようになってきます。
だましに遭った経験を、今後の糧として逆手に取れるようになれば、トレーダーとして大きく成長できるはずです。
エリオット波動を使いこなすためのコツ

ポイント
・波のカウントに正解はあるのか?
・分析ツールとの併用で精度を高める
・成功しているトレーダーの思考法
・継続的な検証と記録の重要性
・独自ルールを作ることで見える新たな視点
波のカウントに正解はあるのか?
エリオット波動を学んでいると、誰もが一度は「正しい波の数え方が知りたい!」と思うものです。しかし実際には、波のカウントに“絶対的な正解”は存在しません。なぜなら、相場は常に変化し続けており、すべての波が教科書通りに出現するとは限らないからです。
たとえば、教科書には「推進波は5波」「調整波は3波」と書かれていますが、リアル相場ではその波形が非常に複雑で曖昧なことが多いです。W字やジグザグ、延長波などが混じり合うことで、正確なカウントはより困難になります。
だからこそ重要なのは、「完璧な波を探す」ことではなく、「自分なりのルールで一貫性のあるカウントができるかどうか」です。つまり、他人と同じカウントにならなくても、自分がそれを軸に戦略を組み立てられるなら、それで十分有効な分析になります。
相場におけるエリオット波動の使い方は、芸術に似ています。同じ風景でも見る人によって描き方が異なるように、同じチャートでもトレーダーによってカウントの仕方が変わってくるのは自然なことなのです。
分析ツールとの併用で精度を高める
エリオット波動は、単体で使うよりも、他の分析ツールと併用することでその精度が飛躍的に高まります。代表的なものが以下の3つです。
- フィボナッチリトレースメント&エクステンション:
波の調整幅や次の波動の目標値を測るのに便利で、特に第3波や第5波の到達点を予測する際に効果的です。 - 移動平均線(MA):
波動の方向感や勢いを視覚的に確認できます。たとえば第3波が始まるタイミングで短期移動平均線が長期を上抜けていると、信頼性が増します。 - MACDやRSIなどのオシレーター系指標:
第5波の終点ではダイバージェンス(価格は高値更新しているのに、インジケーターは高値更新していない)などのサインが出ることが多く、波動の終わりを判断する参考になります。
これらのツールを活用することで、エリオット波動の“仮説”に対してより具体的な裏付けを持たせることができます。複数の分析を組み合わせて、総合的に判断する習慣をつけましょう。
成功しているトレーダーの思考法
エリオット波動を活用して成功しているトレーダーには、いくつか共通する思考パターンがあります。それは、技術的な分析力よりも、柔軟な思考と冷静な判断力を重視しているということです。
たとえば、波動の仮説が外れても落ち込まず、すぐに次のシナリオを考え直す柔軟性があります。相場の流れに逆らわず、「流れに乗る」ことを最優先にしています。
また、成功者ほど波動カウントにこだわりすぎません。あくまで波動は“地図”であり、目的地へ向かうための道しるべにすぎないという感覚を持っています。地図が多少違っていても、大きく道を外さなければ目的地に近づける、という考え方です。
そして何より、彼らは「負けること」を前提にしています。勝ち続けることは不可能だからこそ、損切りや資金管理を徹底し、トータルで勝つ仕組みを作っているのです。
継続的な検証と記録の重要性
どんなに優れた理論も、使いこなすには“継続的な検証”が欠かせません。エリオット波動も例外ではありません。日々のトレードで波を数え、仮説を立て、実際の結果と照らし合わせて振り返る。この地道な作業の繰り返しが、再現性を高める鍵になります。
特におすすめなのは「トレード日誌」をつけることです。以下のような項目を記録しておくと、後から見直す際に非常に役立ちます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通貨ペア/銘柄 | 取引した対象 |
| 時間軸 | 分析に使った時間足 |
| 想定波動構造 | 第○波、第△波といった仮説 |
| エントリー理由 | なぜそのポイントで入ったのか |
| 結果 | 利益/損失、反省点など |
こうした記録を蓄積していくことで、自分がどのパターンに強く、どこでミスをしやすいかが明確になります。それを踏まえて次回に活かすサイクルを作ることで、波動分析の精度もどんどん向上していきます。
独自ルールを作ることで見える新たな視点
エリオット波動を本当に“使える武器”にするには、自分だけのルールを作ることが重要です。なぜなら、波動のカウントは人によって違うからこそ、自分のルールがないとブレてしまうからです。
たとえば「第2波は必ず61.8%までの押しを確認してから第3波を狙う」といった具体的なルールを決めておけば、迷わず行動できます。さらに「第4波は第1波の価格帯に重ならないことを条件にする」など、基本ルールを忠実に守ることで、安定感も増します。
また、自分なりの“得意パターン”を持つことも大切です。たとえば「上昇第3波だけを狙う」「トライアングル後の第5波だけを取る」など、自分にとって成功率の高い波形に絞ることで、トレードの質が高まります。
ルールがあることで判断基準が明確になり、感情に左右されない安定したトレードができるようになります。これが長期的に見て、勝ち続けるための最も強力な武器となるのです。
それでもエリオット波動を使う理由

ポイント
・他のテクニカルとの決定的な違い
・自分のトレードスタイルとの相性
・検証を続けた先に見える“再現性”
・波の理論が教えてくれる相場のリズム
・“こじつけ”を“使える武器”に変える考え方
・この記事のまとめ
他のテクニカルとの決定的な違い
エリオット波動は、他のテクニカル分析とはまったく異なるアプローチを持っています。たとえば、移動平均線やボリンジャーバンドのような指標は、過去の価格データから“平均値”や“標準偏差”を算出してトレンドや勢いを示します。一方でエリオット波動は、「市場は人間の感情の波によって構成される」という前提に基づき、そのパターンを予測しようとします。
つまり、単に価格の上がり下がりを見るのではなく、「今の市場心理はどの段階にあるのか?」を読み解くことにフォーカスしているのです。この“心理分析的”なアプローチが、他の指標にはない深みを与えています。
また、エリオット波動はトレンドの「構造」に注目します。「今の上昇は一時的な調整なのか、本格的な上昇トレンドの一部なのか?」を見極める材料として非常に有効です。このように、マーケットの“全体像”をとらえる力があるのが、他のテクニカルとの決定的な違いです。
自分のトレードスタイルとの相性
トレーダーにはさまざまなスタイルがあります。スキャルピングのような短期売買を得意とする人もいれば、スイングや中長期投資を好む人もいます。エリオット波動はどちらかというと、中長期での相場構造を分析するのに適しており、“待つ”スタイルのトレーダーと相性が良いです。
たとえば「第3波の始まりを狙う」と決めている人は、それが出るまでじっくりと待ち、条件がそろったタイミングでだけトレードをすることで、高確率のポイントだけを狙うことができます。これは、感情に振り回されず、冷静に戦略を組み立てたいトレーダーにはぴったりの戦術です。
逆に、短期トレーダーであっても、エリオット波動を使って“上位足の流れ”を確認し、下位足でタイミングをとるといった使い方もできます。つまり、どんなスタイルでも“軸”として活用できるのが、エリオット波動の柔軟性です。
検証を続けた先に見える“再現性”
一見“こじつけ”のように思えるエリオット波動も、長く使い続けていくことで“ある種の再現性”が見えてくるようになります。もちろん、すべてが教科書どおりに動くわけではありませんが、経験を積むことで、「この波の動き、前にも見たな」という既視感のような感覚が生まれます。
これはチャートを何千枚と見てきたトレーダーだからこそ得られる“直感”であり、“感覚的な再現性”とも言えます。つまり、機械的にパターンを当てはめるのではなく、相場に対する洞察力が磨かれてくるのです。
再現性を高めるためには、やはり継続的な検証と、振り返りの習慣が欠かせません。そして、「自分なりの再現性のある波形パターン」を見つけることができれば、エリオット波動は非常に心強い武器となります。
波の理論が教えてくれる相場のリズム
エリオット波動のもうひとつの魅力は、相場の“リズム”を感じ取れるようになることです。相場はランダムに動いているようでいて、実は一定のリズムやサイクルがあります。そのリズムに乗ることができれば、自然と無理のないトレードができるようになります。
たとえば、急激な上昇のあとには必ず調整が入り、またそこからトレンドが再開される…という流れ。これをエリオット波動では「推進→調整→推進」という基本形でとらえることで、無理なエントリーを減らし、優位性のある場所でだけ勝負することができます。
このように、波の理論は単に“パターン”を見るのではなく、相場全体の流れやリズムを体で感じ取る手助けをしてくれるのです。それが、長く相場に向き合う上での精神的な安定にもつながります。
“こじつけ”を“使える武器”に変える考え方
エリオット波動は、見る人によって解釈が違うため「こじつけだ」と言われることもあります。しかし、その“曖昧さ”を逆手に取り、「自分だけの使い方」として活用できれば、それは大きな武器に変わります。
たとえば、他のトレーダーが見ていないような小波動を分析し、そこに優位性を見出すことができれば、自分だけのエッジ(優位性)になります。「正解が1つではない」からこそ、自分の戦略を作り上げる余地があり、そこにこそエリオット波動の魅力があります。
「こじつけ」と切り捨ててしまうのは簡単です。でも、それを“使える武器”として昇華できた人こそが、真に波動を使いこなすトレーダーになれるのです。
「エリオット波動はこじつけ?実践での使い方とだましへの対応を解説」のまとめ
エリオット波動は「こじつけだ」「当たらない」といった声も多く、批判されやすい分析手法です。しかしその実態は、相場の根底にある人間の心理や感情の動きを“波”としてとらえる、非常に奥深い理論です。確かに、波のカウントは主観が入りやすく、正解のない世界です。それゆえに「使いづらい」と感じる人がいて当然です。
しかし、自分なりのルールを作り、継続的な検証を重ね、他の分析ツールとうまく組み合わせることで、“再現性”や“優位性”を持たせることは十分可能です。成功しているトレーダーたちは皆、「波の仮説」をベースにトレードを組み立て、柔軟に対応しながら相場と向き合っています。
「こじつけ」に見えるのは、まだその本質を理解していないだけ。エリオット波動は、“相場の流れを読む力”を育てる最高のトレーニングになります。だからこそ、こじつけでも、だましでも、自分の中で“使えるロジック”に昇華させることができれば、きっとそれは強力な武器になるのです。
